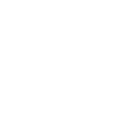山間米は、「甘さ」と「ねばり」が特徴のお米です。
山間米は、四万十川の支流域の谷水を水源にしてつくられたお米です。「甘さ」と「ねばり」が特徴。さめてもおいしいお米です。口に入れた瞬間、お米の甘さが口いっぱいに広がり、噛めば噛むほど甘みが増します。ねばりが強く、もちもちした食感で、冷めてもおいしく、お弁当にも最適です。

四万十川に流れ込む美しい水で育てられています。
山間米の生産地 西土佐は高知県西部にあります。清流四万十川の中流域にある山間地域です。 そんな西土佐には、四万十川に流れ込む5つの支流があります。

深い山あいを縫うように流れる谷水はやがて、山の斜面に作られた段々の田んぼに引き込まれます。ここでつくる米を地元では「入り水の米」といいます。入り水とは、山あいの一番上の田んぼに一番はじめに引き込まれる谷水です。「入り水の米はうまい」と昔からいわれるとおり、米の味は「水」でつくられます。
減農薬など厳しい基準を満たした農家のお米です。
農薬による防除は年に4回以下です。夏は水温が上がり過ぎるのでかけ流しにしたり、浅水にしたり、深水にしたりと、永年の経験と勘で水管理をしています。 環境と農薬のことをちゃんと学んで、水と土とやりとりしながら、米つくりをしています。

品種は山間の気候でおいしく育つヒノヒカリ。
西土佐は、夏は日本最高記録の41℃を記録するほど暑く、冬は大雪が降るほど寒い地域です。秋になれば、四万十の山間部は朝晩の寒暖差がぐっと大きくなり、お米は甘みを増します。十分に熟成させるため、収穫期は他のお米より少し遅く、10月下旬から新米が取れはじめます。目選、手選、色選を行い、山間の気候でおいしく育った西土佐産ヒノヒカリのみが「四万十山間米」と呼ばれるようになります。
この商品は玄米です